【Python】Python入門 print()関数について #11
10回を超えました。
毎日書くと言ったが疲れてたり、眠かったり、家のことだったりで書けてないのが現状。
10回も超えたし、もう少し。少しだけ内容をしっかり書いていきたい。休日限定だけかもしれないが。
今日は print関数 についてもう少し詳しくやっていきたいと思う。
【目次】
【おさらい】
今までは普通に数字を出していただけだった。
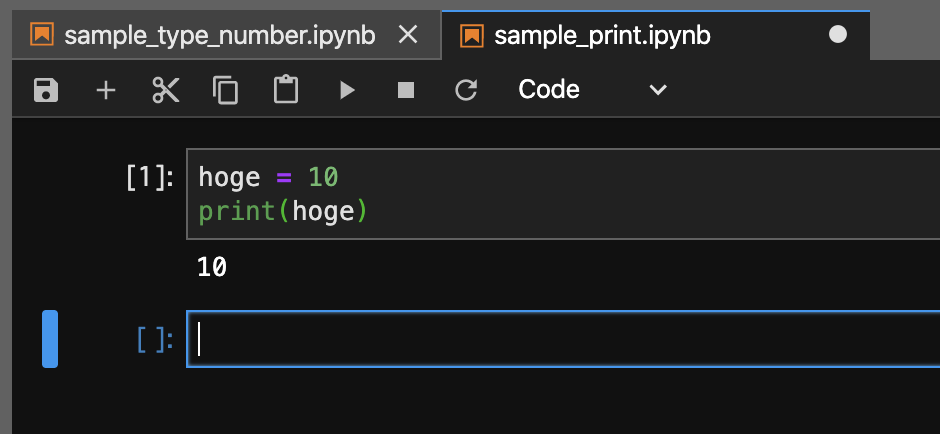
こんな感じで。
文字を単発で出力するだけだった。
他にもいろいろな出力の仕方があるみたい。
なので今回は実際に試してみようと思う
【出力するタイミングで演算を行う】
これはすごく使われていると思う。
実際にはこんな感じ
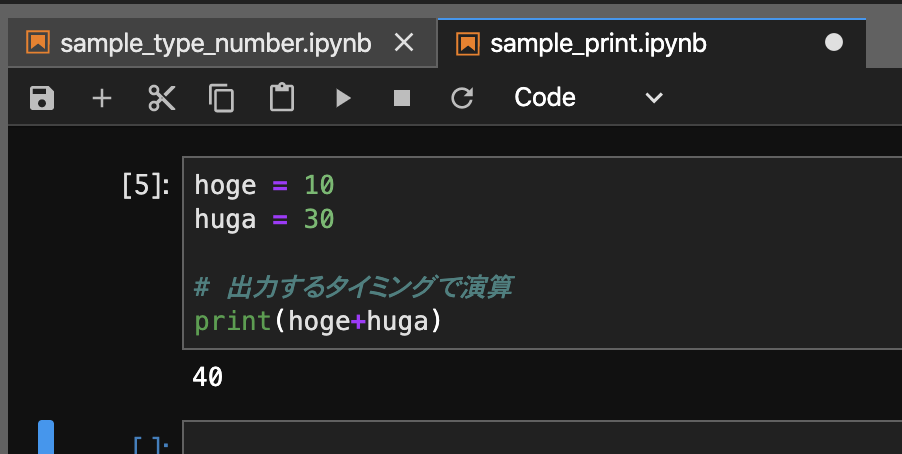
まぁよく見ますね。次。
【複数の値を出力する】
自分はこれあまり使わない
いつもprintを2~3つ書いてる気がする。
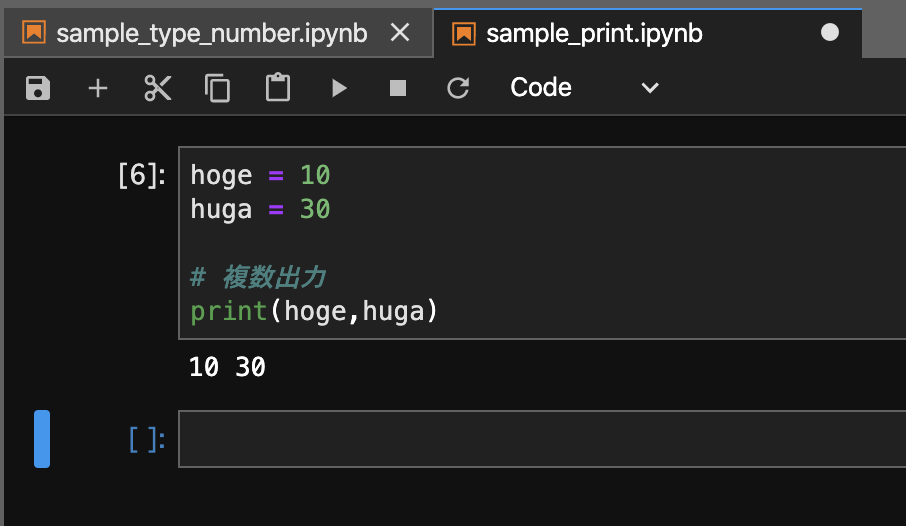
こんな感じで。
変数を , で区切って複数書いている。
出力結果として
数値 数値 と半角スペース区切りで出力している。
もちろん 3つあったり。文字列があっても実行できた。
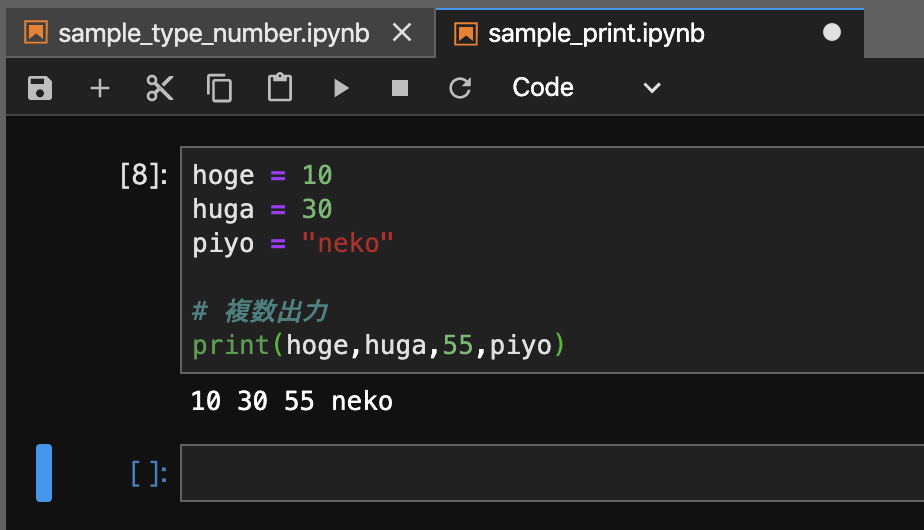
ええやん。次。
【出力の区切りを決める sep】
上例だと半角スペースで区切ってたけど
別に半角スペースじゃなくすることもできるらしい。
ただ半角スペースがデフォルトってことだけ。
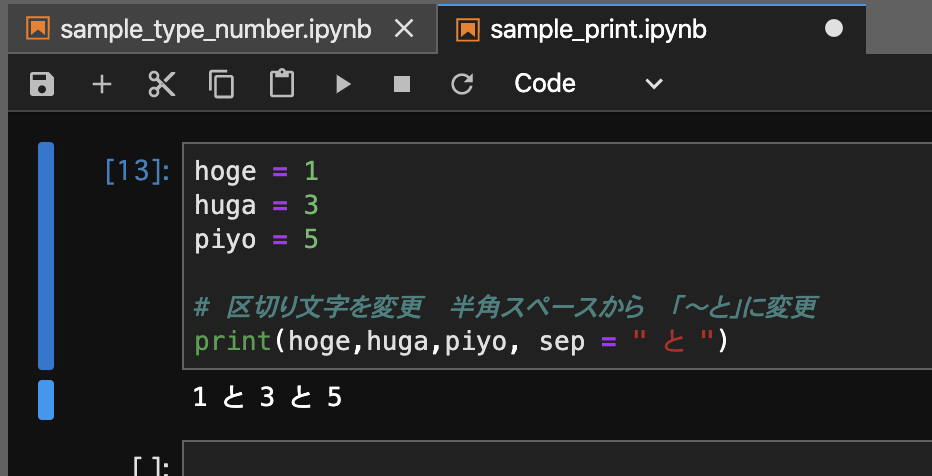
とこんな感じ。
これは知らなかった。
小技感パネェ。。。
sepってのは Separatorって意味
書式はこう
sep="(区切り文字)"
【出力の行末を決める end】
なんと行末も決めれる。
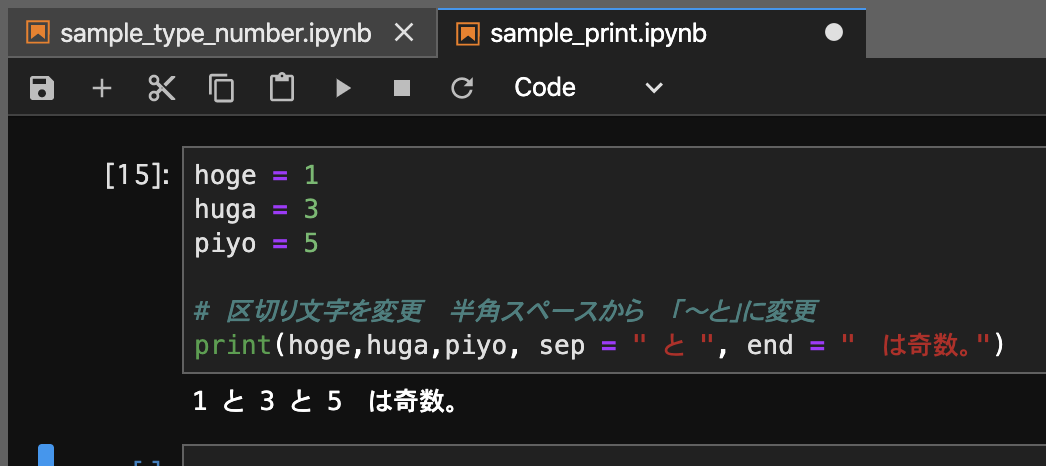
すごいテキストの例題のようなサンプルですこと。
これも知らなかった。
ちなみにデフォルトでは \n (改行)が入ってる見たい。
なので追加でprint出力すると。。。
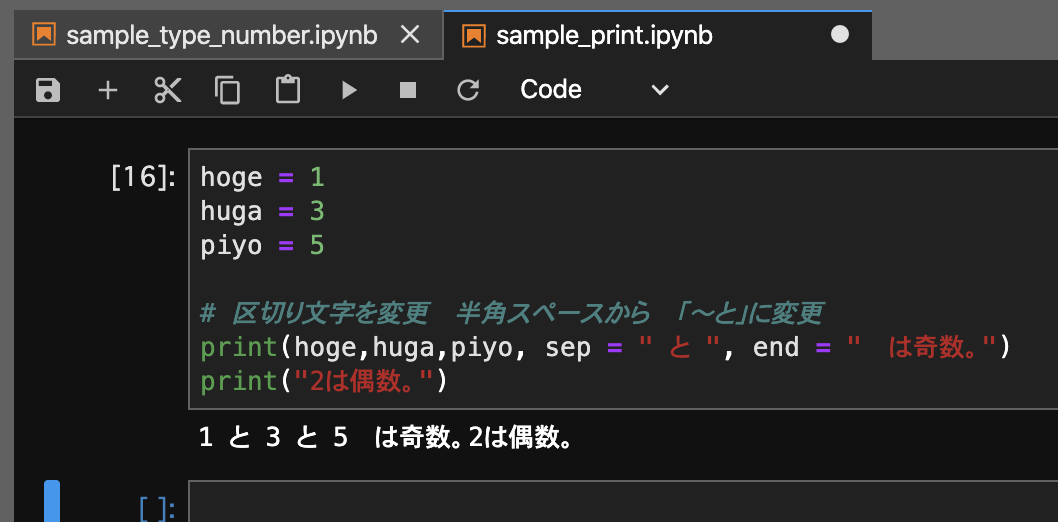
はい。改行がなくなったのでくっつきます。
もちろん改行を追加することも可能。

書式はこう
end="(行末文字)"
【まとめ】
- print出力する前に演算することができる。
- print関数は複数の値を出力できる。
- 区切り文字、行末は指定することができる。
以上。
多分基本的なことなんだろうけど改めて勉強になったなーと思った。
というか基本ができてないから勉強になったんだろうなーと。
はあー。頑張ろー。